レイヤー1とレイヤー2のブロックチェーンの違いは?
Supraコミュニティにご参加ください:https://linktr.ee/supraoraclesjapan
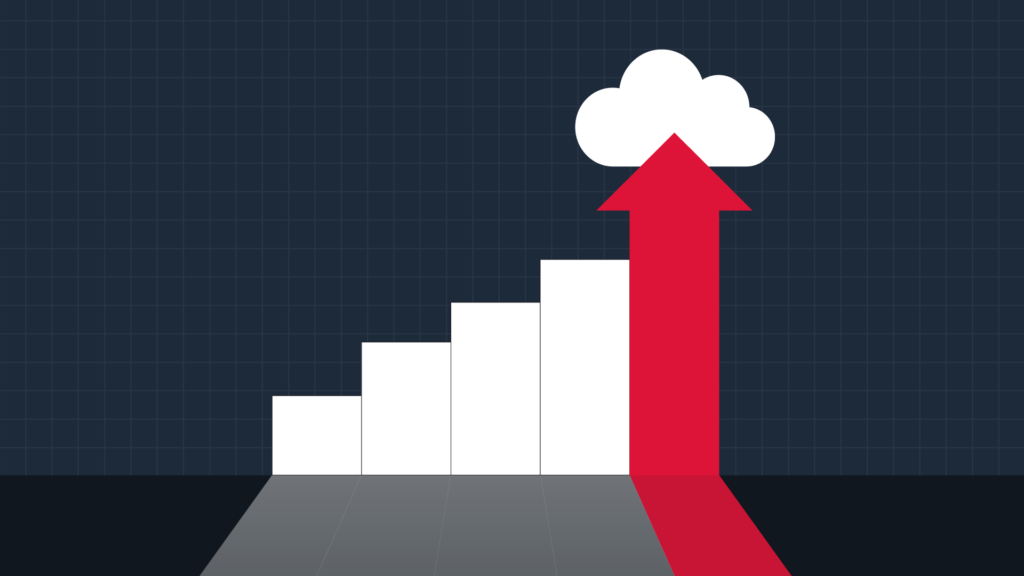
レイヤー2は、レイヤー1のサードパーティによる統合で、ノード数を増やし、システムのスループットを向上させるものです。スケーラビリティとトランザクションの課題の多くは、レイヤー2ソリューションによって解決されると言われています。
ブロックチェーンのスケーラビリティ
セキュリティの向上、取引の簡素化、記録管理など、ブロックチェーン技術のメリットは多岐にわたりますが、普及が進むにつれて、さまざまな問題が浮上しています。
ブロックチェーンに関する懸念事項の1つは、スケーラビリティ(拡張性)です。ブロックチェーンネットワークが高いトランザクションスループットと将来の拡張に対応する能力をスケーラビリティといいます。簡単に言えば、スケーラビリティとは、増加する作業量を管理するシステムの能力のことです。
標準的なアルゴリズムを使用してトランザクションを検証するには、ブロックチェーン内の一連のブロックがすべてのブロックの検証に合格する必要があります。そのため、チェーンが増えると、この作業に時間とコストがかかり、多額の手数料を支払う必要が発生してしまいます。ブロックチェーンシステムを将来的にスケーリング可能にするためには、さらなるコンピュータパワー、サーバー、帯域幅を連動させる必要があります。
分散型システムにおける全てのトランザクションは、ブロックチェーンによる複数のプロセスを経なければなりません。このアプローチには、相当な時間とコンピューティングパワーが必要となります。そこで登場するのがレイヤー2なのです。
ブロックチェーントリレンマ
「分散型ネットワークは、分散性、セキュリティ、スケーラビリティの3つの機能のうち、2つしか提供することができない。」Vitalik Buterinは、これを「ブロックチェーントリレンマ」と呼んでいます。
1999年に科学者が一貫性、可用性、分割耐性定理(CAP)を提唱し、ブロックチェーンのような分散型データストレージは、上記の3つの性質のうち2つしか同時に満たすことができないと断言しています。
現在の分散型ネットワークの文脈では、この定理はブロックチェーンのトリレンマに発展しています。パブリックブロックチェーンインフラは、セキュリティ、分散化、スケーラビリティのいずれかを見送らなければならないという理解です。その結果、インターネット規模のトランザクション量を処理しつつ、広く分散したネットワークで安全なネットワークを構築することが、ブロックチェーン技術の聖域となっているのです。
例えば、同じプルーフ・オブ・ワーク(PoW)方式を採用した2つのブロックチェーンは、分散化の度合いが同じで、ブロックチェーンのハッシュレートを参照してその安全性を判断します。ハッシュレートが上がると確認時間が短くなり、安全性が高まるとともにスケーラビリティが高まります。その結果、継続的な分散化がスケーラビリティとセキュリティに比例することになるのです。
ブロックチェーンレイヤー
スケーリングソリューションは、ブロックチェーンに直接実装されるか、別でありながら依存するプロトコルやネットワークとして実装されるかによって、ブロックチェーン上のいくつかのレベルに分けて実装されます。
レイヤー1のブロックチェーンネットワークは、スケーラビリティ、スピード、セキュリティのために構築されています。レイヤー2のスケーラビリティは、既存のブロックチェーンネットワークのスケーラビリティを高めるために利用できる技術的な進歩や製品を指します。2つのレイヤーの理想的なバランスを見つけることは、ブロックチェーンの受容と分散型ネットワークの成長にとって画期的な発見になるでしょう。
レイヤード方式は、機能の複数の部分を重ねることができるため、あるレイヤーを更新、修正、変更する際に、他のレイヤーに影響を与えることなく容易に行えるという利点があります。これらのレイヤーは、一般的に、ブロックチェーンのアーキテクチャ、コンセンサス、ネットワーク、アプリケーションを構成しています。
レイヤー1 ブロックチェーン
ブロックチェーンの主要なチェーンは、オリジナルのブロックチェーンアーキテクチャとしても知られており、レイヤー1ブロックチェーンと呼ばれています。
最初のレイヤー1ブロックチェーンは、ビットコインで開発されており、そのボラティリティとスケーラビリティの懸念から、現在は主に富の蓄積として利用されています。また、合意形成の方法として、ビットコインはPoW(proof of work)を採用しており、ブロック内では、記録されるトランザクション数が制限されている上、ブロックの確認に1時間程度かかるため、多数の取引を行うには不向きであるとされています。
ここでは、レイヤー1の欠点をいくつか紹介します:
- ブロックチェーンの主要レイヤー1では、依然としてPoWコンセンサス・アルゴリズムが採用されています。この方法は他よりも安全ですが、より多くのCPUリソースを必要とし、システムの速度を低下させます。
- ユーザー数が増えれば、レイヤー1ブロックチェーンの作業負荷も増え、処理速度と容量が遅くなる傾向があります。
レイヤー1ブロックチェーンのスケーリングは、以下の方法で行うことができます:
- レイヤー1は、PoSコンセンサスによってスケーリングできます。これは、イーサリアム2.0で使用されるコンセンサスメカニズムでもああります。この仕組みは、ネットワークの利害関係者のステーキングに基づいて新しいトランザクションデータのブロックを認証し、プロセスを高速化するものです。
- シャーディングは、過負荷なワークロードに対するスケーラブルなソリューションです。簡単に言うと、シャーディングは、トランザクションの検証と確認の作業を小さく管理しやすい塊に分割し、それをネットワーク上に分散させることで、より多くのノードが処理能力の恩恵を受けられるようにするものです。ネットワークはシャーディングを並列に処理するため、複数のトランザクションを同時に順次実行することができます。
- ブロックのデータストレージ容量を増やす。
これらのスケーリングオプションを組み合わせると、ネットワークのスループットが向上しますが、ブロックチェーンの利用者が拡大する中で、レイヤー1としての本来の目的から外れていっているように見えます。
レイヤー2ブロックチェーン
前述の通り、レイヤー2ブロックチェーンは既存のブロックチェーン上に構築され、スケーラビリティやスピードといった機能を提供する仕組みです。
元々レイヤー2のソリューションは、ビットコインのスケーラビリティの問題を解決するために開発されました。ライトニングネットワークは、マイクロペイメントチャネルを活用し、ビットコインのトランザクションをオフチェーンで行えるようにしたもので、その本質的な例と言えるでしょう。この場合、レイヤー1のチェーンでは、チャネルの開閉のみが記録されます。
その他のレイヤー2のスケーリングソリューションを紹介します:
ネスト型ブロックチェーン
ネスト型ブロックチェーンは、レイヤー1のブロックチェーンの上で実行されるレイヤー2のブロックチェーンです。言い換えれば、レイヤー1がパラメータを定義し、レイヤー2がプロセスの実行を手配します。メインチェーン上には、多数の層のブロックチェーンが存在する場合があります。
例えば、OMG Plasmaプロジェクトは、イーサリアムのレイヤー1プロトコルのレイヤー2ブロックチェーンとして機能し、より安価で迅速な取引を可能にしています。
ステートチャネル
ステートチャネルは、ブロックチェーンの各レイヤーの双方向通信を可能にします。ステートチャネルは、マイナーを排除し、スマートコントラクトに従って行動することで機能します。マイナーが操作に関与しないため、待ち時間が短縮されます。ステートチャネルは、ビットコインのライトニングネットワークが例として挙げられます。ライトニングネットワークは、ユーザーが一連のマイクロトランザクションを一定時間内に完了させることを可能にします。
サイドチェーン
レイヤー2のブロックチェーン技術では、スケーラビリティのオプションとしてサイドチェーンが使用されています。サイドチェーンは、メインブロックチェーンとは独立した、スケーラビリティと処理速度に特化した独自のコンセンサス方式を特徴とするチェーンです。メインチェーンは、トランザクションデータの確認、セキュリティの維持、サイドチェーンの文脈での紛争解決などを行う必要があります。
ZK-Rollups
レイヤー2のソリューションで、ゼロ知識(ZK)プロトコルを用いた数学的証明により、トランザクションの正当性を保証する仕組みです。ZK-Rollupsは、大量の送金処理を1つのトランザクションにまとめることでスケーラビリティを向上させます。
まとめ
では、レイヤー1とレイヤー2、どちらのソリューションが課題解決により有用なのでしょうか?
理論的には、既存の全てのソリューションには利点と欠点があり、全てのコンテキストでうまくスケールするわけではありません。さらに、いくつかのソリューションの安全性は示されていないか、特定の理論的条件下でのみ確立されています。
この問いは、スケーラビリティに取り組む際の問題提起であり、議論を生み続けています。2つのレイヤーの適切な組み合わせを見つけることが、今後数年間のブロックチェーンの普及とネットワークの拡大にとって、ゲームチェンジャーとなる部分なのかもしれません。
暗号通貨業界の将来に関連するあらゆる事柄について、より深い知識を得るには、Supraアカデミーセクションのコンテンツは有用な情報源となるでしょう。全ての記事は情報提供のみを目的としており、いかなる種類の投資アドバイスと見なされるものではありません。